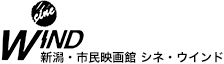シネ・ウインド上映企画会議 毎週土曜19時~
※8/16㈯の会議はお休みです 次回は8/23㈯
映画の所在地
6月の半ばに、シネ・ウインドで「ノスタルジア」を観た。「女だけがこれほど神に縋るのはなぜ?」という重々しい台詞に面食らったまま2時間の鑑賞を終え、その熱量が冷めぬまま、半ば勢いでわたしはシネ・ウインドの上映企画部に出てみることを決めた。初めて会議に参加した日は、まさに「ノスタルジア」の世界観を再現したような、大雨が降る土曜日だったことを思い出す。
あっという間に2ヶ月が経った。個人的なことではあるけれど、映画との関わり方についてぼんやりと考えていたことを書いてみたい。


20代の大半は東京で過ごし、週末になれば電車に飛び乗ってどこかの映画館に向かうような日々を送っていた。わたしは映画と生活をまぜこぜに記憶してしまうきらいがあるようで、観た映画を思い出すときには必ず街の風景が一緒に思い出されるのだった。たとえばホン・サンスなら有楽町、エリック・ロメールは池袋、侯孝賢は阿佐ヶ谷というふうに。映画を観て街を歩くたびに、東京というよそよそしい街が少しずつ自分に馴染んでいく感覚が好きだった。
2年ほど前、生まれ育った新潟に戻ってきて少しほっとした気持ちで暮らしながら、前と同じようには映画を観ることができない気がしていた。東京で通っていた映画館と自分が今暮らす場所とは、最早200km以上の距離がある。その物質的な距離と同じくらい、心の距離が空いてしまったことに気づいたのだった。そもそも映画を街の体験の一部として捉えていたようなものだから、PCを開いてサブスクリプションで観たってなんだか味気ないなあ、という思いもあった。新潟のサッカー熱にあてられて、週末はスタジアムに足を運ぶ生活に変わっていった。

ところがひょんなことから、前述のとおり上映企画部に参加し始めて、映画に対する気持ちがまた少しずつ変わっていった。上映企画部では、上映作品の選定において「シネ・ウインドに足を運ぶ人に届けたい作品か」「どうしたらこの映画の魅力が伝わるか」という観点で議論が交わされる。それまで個人的な体験に過ぎなかった映画鑑賞という行為のその先に、「誰かに届けるもの」という視点が加わった。言ってしまえばほぼ諦めかけていた映画との向き合い方に、新たな可能性が生まれた気がして、嬉しい気持ちになった。月刊ウインドに掲載するための作品紹介を書きながら、観た作品が自分の中で重みをもって位置づけられることも新鮮だった。
そんなふうに過ごしていたところ先日、新宿にあるシネマカリテが閉館することを知った。言いようもない寂寥感を感じながら、シネマカリテで観た映画のことを思い出す。最も印象に残っているのは2022年に上映されたロベール・ブレッソンで、「たぶん悪魔が」に出てくる厭世的な青年の猫背がちな歩き姿や、「湖のランスロ」での甲冑の鈍色が重く光るショットが浮かぶ。あの天井が低い劇場と、新宿の雑多な街並みがオーバーラップして。
かつて足を運んだものの閉館してしまった映画館はいくつかあって、それらを思い出す度に、上映を待ちながら所在なく佇んだロビーや、過去作品のポスターが埋まるように貼られた壁はもう存在しないのだと気づき、少し悲しい気持ちになる。そしてこの寂しさに慣れることはないのだろうと思う。

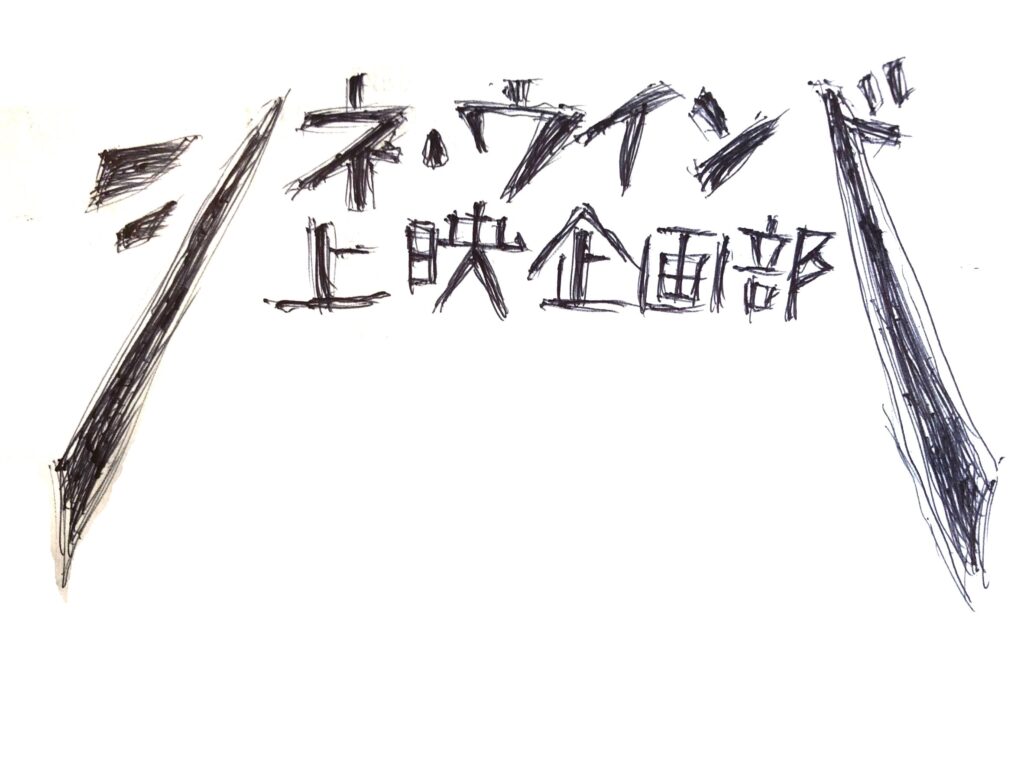
シネ・ウインドに通うようになってから、少し歩けばすぐに川沿いに行けるところが好きになった。川の近くにある映画館は全国を探してもそう多くはないはずだ。映画を観終わったあと、信濃川のきらめく川面を横目にやすらぎ堤を歩きながら、菊地凛子の巻いていた青いマフラーやジーナ・ローランズの鬼気迫る演技に思いを馳せた一昨年の秋、新潟って良い街だな、としみじみ思ったのだった。

できるだけ多くの人に、シネ・ウインドで映画を観る体験をしてほしいなと思う。スクリーンに向かいながら一人きりになる感覚や、映画を観終わったあとの呆然としてしまう瞬間を味わってほしいし、映画にまつわる多くの記憶が、新潟の街並みと重なっていたらいいなと思う。そのために自分ができることがたくさんある。そのことが喜ばしく、ひとつずつ、いろんなことをやっていきたいと思う。これからも色々な映画を観たいし、また新しいことを考えて、映画の知らなかった側面を見つけていきたい。それらがシネ・ウインドのこれからに繋がれば嬉しい。
中村理奈
シネ・ウインド上映企画部では、上映作品の選定や、作品紹介をお手伝いしてくれる方を募集しています。上映企画会議は毎週土曜19時より、事務所2Fフリースペースにて。映画館の運営に興味がある方、見学・入部など、お気軽に劇場スタッフにお声掛けください。