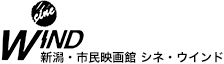『十二人の怒れる男』原題:12 Angry Men 1957年 アメリカ映画 監督:シドニー・ルメット 製作/脚本:レジナルド・ローズ 撮影:ボリス・カウフマン 編集:カール・ラーナー 美術:ロバート・マーケル メイクアップ:ハーマン・バックマン 助監督:ドン・クランゼ 音楽:ケニヨン・ホプキンス 製作/主演:ヘンリー・フォンダ 当館公開日:1999年5月8日
これはほぼ全編が陪審員室での話し合いで進められていく、法廷劇の名作。その一室の対話劇で、偶然集まった男たちの性格や感性がジワジワ滲み出てくる、ヒューマニスティックの白熱が凄かった。原作はレジナルド・ローズによるテレビドラマで、映画脚本も手掛けました。元軍人のシナリオライターで、実際に陪審員となって審議した経験を基にした作劇だそうです。18歳の少年が父親を刺殺した事件の審議にあたる12人の陪審員。もう少年が有罪なのは明らかですが、最初に決をとりましょうかとなりまして、12人中11人が有罪。1人が無罪に手を挙げました。ヘンリー・フォンダ扮する8番陪審員は「無罪とは言いませんが、まだ決められないんです。小さな疑問がいくつもありまして。話し合いませんか」と言いました。「いいでしょう」と納得する人。暑くて面倒で早く帰りたい人。こいつは絶対有罪だろうと決める人。そうして話し合いが始まって、この事件がどういったものだったのか。少年が殺したのか、そうとも言い切れないのか。そのときどんなことが起こっていたのか。議論していきます。
見どころとしてはまず、ヘンリー・フォンダ陪審員の慎重さ、真剣さ。一人でも考えて考えて、有罪と決めた11人を相手に疑問を呈した。「天邪鬼気取って勝手を抜かすな」と興奮していく男たちを相手に、冷静に説いていく姿。他者の人生を左右する案件を、曖昧なまま終わらせられないという真剣さに、ひとりまたひとり感化されていくところ。感情が昂って、段々といろんな人間性が出てきます。何かを決める責任、掘り下げて話し合うことがどれだけ重要か。同時に様々な人の集まりという怖さと難しさ。そうして映画の調子はどんどん熱く、スリルが出てきます。決め付け、偏見のような根付いた考えがどれだけ視野を曇らせるか。感覚を鈍らせるか。そういう議論ならではの緊迫感も見どころですね。
社会派映画の名手であるシドニー・ルメットが33歳で映画監督デビューして見せた。ヘンリー・フォンダは製作も務め、意気込んで主演しました。その勇気と冷静さで、銃や格闘じゃない、考えることを諦めない映画ヒーローを見せました。それに対峙するリー・J・コッブ、E・G・マーシャルの演技も見事でした。キャメラマンはロシア出身のボリス・カウフマン。『波止場』でアカデミー賞を獲っています。白熱していく演技、議論をじっくり捉えて、この映画に迫力をもたせています。ということで法廷劇、密室劇、会話劇としてみても、これは重要な名作ですね。
宇尾地米人