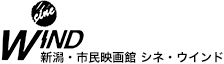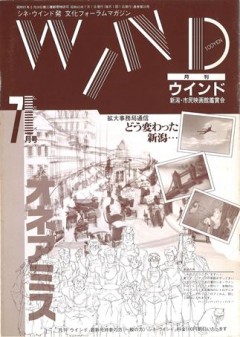シネ・ウインド30年目記念インタビュー 第5弾 「王立宇宙軍 オネアミスの翼」監督 ガイナックス 山賀博之
※このインタビューは、月刊ウインド2015年4月号に掲載されたものです。
1本の映画を10回ずつ
山賀◆シネ・ウインドに最初に来たのは1987年の5月だったかな。
――「王立宇宙軍 オネアミスの翼」の公開はその少し前ですね。
山賀◆公開はその年の3月14日だった。
――新潟だと最初の上映はシネマかどこか。
山賀◆公開してしばらくは全国行脚してたんで、それが終わって完璧に仕事がない状態になって新潟に戻ってきたのが5月くらいだったと思う。北村くん(当時の月刊ウインド編集長)は中学の同級生。
――それまでシネ・ウインドのことは?
山賀◆知らなかった。だから、北村くんから電話がかかってきた時に、そんなことやってるんだって、ちょっと驚いた。
――北村さんから連絡をとってインタビュー(月刊ウインド87年7月号掲載)をお願いしたんですよね。最初にウインドを見た時は、どう思いました?
山賀◆ライフ閉館の話はなんとなく聞いてたけど、ウインドができたっていうのは知らなかった。そういう形っていうのは、新しい、これからの映画館みたいな感じはしましたね。
――前に聞いた、同じ映画を10回見たという話がおもしろかった。「ベアーズ」?
山賀◆「がんばれ!ベアーズ」だったらよかったんだけど(笑)。もうちょっと有名作品にしておけばよかった。嘘はつけないんだよね。もっとカッコいい巨匠の作品にしておけばカッコつくんだけど、「がんばれ!ベアーズ」ですらない。「がんばれ!ベアーズ」の第二弾。第一弾はアカデミー賞で賞を取ったりして超有名だけど、第二弾は誰も知らない。
――なんでそれだったの?(笑)
山賀◆たまたま(笑)。高2の冬かな。知識も関心もなかったから、映画というものに無頓着だった。「10回見ろ」っていう淀川長治さんのアドバイスがおもしろいな、と思って、じゃあ、近所で何やってるだろって考えた。ライフに行けば安かったのに、知識がなかったから封切館に行ったんだよね。当時は2本立てが普通だったのに、その時は珍しく1本立てだったから、1日いれば6回、2日通えば10回見れた。入替なしの時代だから。あ、そうか、そういう意味では、なんで「がんばれ!ベアーズ特訓中」なのか、必然性があったね。2本立てじゃなかったという(笑)。
10回見たことによって初めて映画がどのように作られたかがわかった。最初は普通にストーリーを見て、2回、3回は段々飽きてきてつまらなくなる。でも、4回、5回と見るうちに、話の組み立てとか、セリフとか、ライティングとか、音楽の入れ方とか、芝居とか。俺、これを決めることはできるな、と思ったわけよ。じゃあ他の映画も淀川先生が言うように10回ずつ見てみようと思って。新潟市でやってるものをかたっぱしから見て、三条の名画座に行ってそれも見尽くすと、鈍行で東京に行って東京の名画座で見た。親戚の家に泊まってね。親から昼飯代をくすねる形でお金をなんとか工面して。
――そこまでしたモチベーションは?
山賀◆仕事にしようと思ってたんですよ。「がんばれ!ベアーズ特訓中」を10回見たことによって、あ、この仕事、俺、できると思ったんで。そもそもの発端が淀川長治さんの書いた記事。若いヤツが「映画監督になりたい、どうやったらなれるか」と聞いてくるんだけど、「そんなことがあってたまるか。そんな近道はないんだ」「強いて言うなら、1本の映画を10回ずつ見なさい」と。そこからスタートしてる。なりかたはないんだろうなと思ったから、素直にいろんな映画を10回ずつ見るという教えを守ったわけですよ。
――他の映画も10回ずつ見たんですか?
山賀◆そうそう、世の名作と呼ばれているものも含めて。岩波ホールも行ったし。岩波ホールは入替制だったけど、他は朝入ったら、夜中までずっと見てた。
――変な人だと思われたんじゃない?(笑)
山賀◆うん、映画館の人に「あれ、あなた、昨日、来たじゃない?」なんて言われて。こっちは体育会系のトレーニングみたいなつもりでやってるから、もう辛いとかそんなんじゃないの。壁打ちやってるみたいなもんだから。内容覚えてるとか覚えてないとかじゃない。おもしろい映画か、いい映画か、悪い映画かも関係ない。とにかく一日映画を見ていよう、ってそれだけをやってた。
――それをやった人って他にいたのかな。淀川さんの文章を読んだ人は他にもいたと思うけど。
山賀◆さぁ~聞かないですね。そういう意味では、自分はなんか変なことやるっていうのはあるよね。変わってるんですよ、すごく。
――今、若い人に同じ質問をされたらなんて答えます? 映画監督になりたいって。
山賀◆僕にインタビューで聞いてくる人は、この話を知ってるから、逆に、10回見るんですよね?って言ってくる。あなたは10回見てもしょうがないと思うよって。だって映画が好きな人が10回見ても楽しんでるだけだから。僕は映画が好きじゃなかったから、10回見ることに意味があったけど。映画が好きな人が年間600本見てますとか、1本の映画10回ずつ見てますって言っても、それはあんた、好きで見てるんでしょ。勉強でもなんでもない。それは娯楽。すごく優秀なお客さんにはなるだろうけど。
だから、アドバイスすることってあんまりないな。その人、その人の「あ、この人のこういうところが凝り固まっているな」ってところを見つければ「もうちょっとこうやったらいいよ」っていう話はするだろうけど。普遍的なものってないと思うな。
↑ 月刊ウインド 1987年7月号 インタビュー掲載号。「八億円つかっちゃった男」という、すごいタイトルでした。
↑ 月刊ウインド 1988年7月号 「オネアミスの翼」上映時の月刊ウインド。中面の「あ・ら・かると」欄には、山賀さんのコラムも載っています。
2本目のための人格改造
山賀◆僕も今、原点回帰の時なので、このインタビューが何かのきっかけのような気がしてね。新しいことをやろうとしてるんだけど、新しいといっても、前に「オネアミスの翼」があったでしょ? その2本目なのね。この28年間は2本目のための訓練期間であって、そういう意味ではちょうど戻ってるの、あの当時に。この28年間いろいろあったけど、さて、と。すごいタイミングだな、と思った。
――今、改めて、さて、と思ったのは、何かあるんですか。
山賀◆2本目だから(笑)。これも10回見るのと同じで、普通の人は28年もかけて1本の映画を作らないと思うんだけど。僕の中では自然なことであって。1本終わった後で、必要なのは人格の改造だなっていうのがあった。俺、このままでもう1本作ったらどうなの?って。いろんなコンプレックスもあるし、問題意識の低さもあるし、いろんな意味で、もう1本作っても俺はアニメオタクのための生産者にしかならないな、っていうのが自分で受け入れがたいのね。だって映画好きなわけでも、アニメ好きなわけでもない(笑)。そこが原点だから。自分にとって意味のあることをしたいと思った時に、自分が誰に対してでもなく、自然にこれを作ります、っていう気分になれなきゃ2本目を作る意味がないわけ。1本目はスタートだから、スタートを切ることだけで意味がある。何やっても楽しいし、新しい。2本目は違う。もう楽しいものはないわけよ、初めてじゃないから。2本目はもっと自分のものじゃないといけない。そう考えた時に、人様の前にお出しできる自分じゃないってことに気づく。87年当時、自分で自分を顧みて、こんなヤツが作った映画を俺は見に行きたくないって思った(笑)。
そのためにはどんなヤツになるべきなのかなっていうのがあったから、人格改造。反省してるわけじゃないんだけど、人情みたいなものから遠すぎる。クールならクールでいいんだけど、もっと情のようなものに触れる中でのクールを確認すべきだと思った。単純に、若いヤツがそんなのつまらないよって撥ね除けるのは、自分の中では、付き合いきれない。若いヤツが、いろんな事態があると、たとえば“イスラム国”の人質事件とか、俺に関係ないから、って。そのとおりなんだけど、もう一コ、そこに情のようなものを感じながら「関係ないしね」って言うんだったらいいんだけど。そこがね、あの頃の自分は少し足りてないんだよね。たぶん、一種恐怖。自分というものの弱さを包むための、うちの会社の作品でいうと「ATフィールド」、要するに自分を防御するためのバリアのようなものが若い頃は強いわけですよ。そんなヤツが作った映画なんて共感できないし、共有できないと思った。少なくとも自分はね。だとしたら、自分で自分が好きになれるものを考えよう。それが大きなテーマ。やってみると意外と難しかった。時間もかかった。
――28年かけて、どう? 進んだ?
山賀◆うん。少なくとも調和は取れてきたね、自分の中で。
「蒼きウル」
――具体的に、2本目はいまどの辺り?
山賀◆今はお金をかき集め中。先行する短編の製作、そして2時間の本編の脚本をぼちぼち練っている。28年という長い年月があったんで、練ってるものはたくさんあるんだけど、改めて2015年の自分が考えたことを書かなければいけないんで、そういった意味では今までのあれやこれやは一回チャラにした上で書いてる。役割は原作・脚本・監督。タイトルは「蒼きウル」。英題は「Uru in Blue」。
――完成はいつを目指しているんですか。
山賀◆脚本は夏。全体の完成は2018年。
――3年…。でも、あっという間だよね。
山賀◆この28年のことをたった3年でと思うとちょっと寂しいものもあるんだよね(笑)。できればの話だけどね。
――楽しみですね。
山賀◆僕も楽しみなんですよ。どうなっていくのやら。自分が今こうして生きているということの感触を、こうやって作品というものに作れるというのは、そんなことができる立場にいる人ってあんまりいないと思うんだよね、世界的にも。すごくありがたいことだと思うんで、これはフルに使わせてもらおうと。
――やっぱりアニメなんですよね。
山賀◆アニメです。日本で作る以上、僕はアニメを選びたい。自分がやってきたというのもあるけど。アニメってすごく日本的だと思うんだよね。実際、世界中に広がってるし、アニメ映画をちゃんと作りますって言ったら、世界中でお金を集めることができるのは確かなんで。商業性というものもある。商業的に成功するってことは、同時に人が求めているということであって、その人のパーソナルなことに直結していること。そういう意味で、アニメは少なくとももう1本は作る価値があると思ってるんです。その先はわからない。
ドラマ「アオイホノオ」
――新潟でも少し遅れて放送されたので、見てましたよ。
山賀◆あれは僕らが作ったわけじゃないし。毎週見てますって言われても、「あ、どうもありがとう」、でも俺のもんじゃないけどなって。不思議な体験ですよ。普通はないでしょ、自分らの学生時代のリアルな再現ドラマなんて。
――「山賀」さん役はムロツヨシさんだったけど、本当にあんな感じだったの?(笑)
山賀◆ま、あんなもんですよ。映画が好きで入った学校じゃなかったんで、これから自分が職業として身を立てるためにどうしよう、どうやったら一生食いっぱぐれなく生きられるかってのが大学に入った時のテーマだった。若干、演出は入ってるけど、基本的に嘘は描かれてないね。主人公にふたり女の子がついていたのは嘘だけど。嘘はあれだけだから。
――山賀さん本人も出演してましたね(笑)。
山賀◆出たくなかったんだけど、こういう縁だし、断るのも大人げないねってことで。芝居とか大嫌い。苦手なんだもの。映画をやろうと思った時に、役者になろうとだけは一瞬たりとも思わなかった。普通、映画をやろうと思ったら、映画に出ようと思うじゃないかと思うんだけど、そういう感じではないと思ったんだ、自分で。レンズの後ろにいる人だとずっと思ってたんだよね。前に立つ人は俺なんかじゃない、特殊な人なんだって。
福島にスタジオを開設
――最近、新聞記事になったじゃないですか。福島のこと。スタジオを作るんですよね。
山賀◆福島県三春町にスタジオとアニメの作り方を展示するようなミュージアムを。地元の若い人を集めてやるんで、始めの1年は学校でしょうね。ゼロからのスタートですよ。
――やりたい人はいっぱいいるでしょ?
山賀◆ありがたいことにね。昔に比べるとすごいよね。昔はちゃんと大学卒業してアニメ業界入りたい人はいなかったけど、今はほとんど大学出てる人ばっかりだもんね。昔だったら考えられないよ。あなたの生涯賃金であなたの親が払った教育費はぜったいに元取れないよっていうのが丸わかりなわけで。でもそんなの関係ないんだね。今の人は逆に僕が職業を選んだ話をするときょとんとする。「食うためにやってるんだから」って言うと、「えっ、それだけですか?」って。僕らの頃はまず第一に食えるかどうか、っていうのがあったと思うのね。食えないけど、これが好きだから頑張りますっていう人は、いたとは思うんだけど、そんなに多くはなかったと思う。今の若い人たちはむしろ、逆転してるね。食える食えないはもちろん重要なんだけど、それよりも自己実現として、その職業を選んでいいのかどうかって、僕らの頃より強く感じているようだね。
砂上の楼閣と諸行無常
――新潟には何かありますか、バックボーンとか。
山賀◆ありますけど、あんまりノスタルジーでとらえてはいないですね。ただ、現在の自分のセンスを新潟がどう作っていったのかはすごく検証しました。原風景としての景色とかね。外に出るとわかるじゃない、あれ、他にはない新潟の風景だったんだ、とか。
それと、新潟地震でも被害がそれで起きたんだけど、新潟は砂の上に建っている。砂上の楼閣だよね。僕ら、子どものころは、砂も含めて土って呼んでたけど、よそに住んで初めてわかった。これは土じゃないんだ、砂だって。それが特徴だな、と思った。砂の上に建っている町なんだよね。何もない平面の上にぽかっと建っている。そこに何があるかは、評論家じゃないんで、そこまで分析する必要はないと思ってるんだけど、ただ、その無常観っていうのかな。新潟は古いものを大事にしないって、批判的に言われるでしょ。なんでもかんでもぶっ壊すって。僕はそういうの嫌いじゃない。萬代橋がなくなったらさびしいけど、萬代橋だって人間が作ったものだから、いつか消えてなくなるものだし。それが生まれ育ってきた新潟市のセンスのような気がする。諸行無常なのよ、何か(笑)。それはありがたかったな、と思う。そういうことをこの町は子どもの僕に教えてくれた気がする。虚しいものであって、砂の上にあって、いずれは砂にかえっちゃうんだよ、みたいな。砂漠に行くとすごく心が落ち着くのね。故郷を感じる。新潟は砂漠ではないんだけど、意識の中であるんだな。ドバイとか行くとね、ホントに砂漠の中にぽこっと町が建ってて、なんとも言えず、懐かしさを感じる。
手軽じゃないもの
山賀◆18歳までずっと新潟市です。シネ・ウインドにいたのは、87年から92年くらいまでの間だから5年間ですね。
――5年もいたんだっけ!? 山賀さん、あの頃よくここ(フリースペース)にいたよね。
山賀◆当時新潟で何か新しいことっていうのか、若い者が集まってなんかやろうみたいな勢いがあるのはシネ・ウインドくらいしかなかったんじゃない?
――今のウインドを見て、どう思いますか?
山賀◆新潟全体の状況をみると、齋藤さんなんかがいろいろ訴えてもおじさんたちが聞く耳持たない状態だったあの時代とは違うと思うね。今は文化的なこと遊ぶことに対してみんな積極的だし。唯一無二だった時代と、念願かなってみんながそういう活動をし始めた今とでは、シネ・ウインドの意味が変わってきちゃうのも仕方ない。映画というもの自体の意味もどんどん変わっていくわけですから。
80年代の映画は、最初に考えたのは、映画館はなんで町の中心にあるんだろうってこと。中心部は土地代も高いのに、それを町として認めているわけ。商業的に成り立つっていうのはそういうことでしょ? 映画を見にいくことを中心に文化的活動があると思ってたわけだよね。そこが楽しみでもあるし、誇らしいことであるし、よいことだったんだよね。
段々時代が変わっていくと中心部に映画館がなくなってくる。見る側としては郊外のシネコンは大歓迎だった。シートはよいし、快適だし、いろんな映画をたくさんやるし。便利になって手軽になると当然、お祭り的な意味での文化の中心から外れていって、コンビニエンスになっていく。手軽なのはよいと思って、みんなそのとおりに努力して手軽になってきたと思うんだけど、映画が手軽になりすぎて、ひとことで言うと価値が下がった。
でも、将来展望でいうと、これからはもう1回映画かな、って思うんだよね。これはスピルバーグも予想してるんだけど、これだけ映像が普及しちゃうと、手軽に楽しめる、タダで楽しめる映像か、高い金を払ってわざわざ出かけていく映画かの、二極化が起きるだろうと。僕もそれはそう思う。みんな、町の中心での祭りを求めているのは確かだと思う。その祭りの中に演劇もあるだろうし、踊りもあるだろうし、いろんなイベントがあるだろうけど、その中に、映画がなくなる感じはしない。映像はなくなる気がしない。
東京駅でプロジェクションマッピングしただけで、大混乱になるくらい人が集まる。たいしたものは映ってないんだよ。でも見たいんだよね。見たいし、体験したい。それはそこに行かなきゃ見れない、というのが大事であって、だからみんな行くんだよね。タダって言ったって、時間と交通費とを考えたら、お金は払ってるわけ。そこに行かなきゃ見られない映画っていうのは、テレビやパソコン、携帯などでタダで見られるお手軽な映画とは分離して扱われるようになると思う。手軽になればなるほど価値が下がるのは確か。でも、人は価値を求めるから。手軽じゃないものに価値を求める。手軽じゃない映画が出てくると思う。これからの映画はむしろ、高くて不便で(笑)、何のためにそんなのに出かけていくの?とかお母さんに怒られるようなものを求めるべきだと思う。
手軽なものは段々粗製乱造になっていかざるを得ないんだよね。アニメ業界もそう。お客さんの数は増えている気がするのに、粗製乱造でどんどんいっぱい作る。手軽に携帯でも見られるようになっていくと、アニメというものの価値自体が明らかに80年代と違う。メジャーになったらなったで価値が下がっている。みんなが注目してるのに儲からないという不思議な現象が起きてる。価値があるものなら大胆に出るべきだと思うな。価値があるものにはみんな、お金を払おうよ。その方が楽しいよ。不便なところに行ってみようよ。
出しゃばらなければ
――シネ・ウインドはデジタルになって、他の映画館と同じところにやっと並んだところ。
山賀◆でも、それはそれとして、長いことやってきたブランドのようなものはできてきたよね。それは昔はなかったわけだから、利用すべきだよね。シネコンで見るのと、ウインドで見るのとは違うっていう雰囲気は重要。
――あの映画ウインドでやるなら見に行くのに、みたいな声はありますよ。逆もあるけど。
山賀◆文化的ブランドというといやらしいけど、それは重要だよね。実は、それはうちもそうなんだ。ブランドしかないの。実質的なものはない。看板だけ。看板があれば、福島にスタジオ作りますっていうだけで、NHKがニュースで取り上げてくれる。シネ・ウインドも看板はちゃんとできてきたと思う。
――まだまだだけど、それはそうですね。齋藤さんという看板もいるし(笑)。
山賀◆そう、そこだよね。でもその後はどうするんだろ。そこは気になる。興味があるね。
――最後に、シネ・ウインドの会員や月刊ウインドの読者に何かひとこと。
山賀◆映画でもなんでも、こういう活動がおもしろい時代になってきていると思うんです。特に、新潟のような地方は。
齋藤さんは確かに一種天才だし、越えられないように感じるかもしれないけど、いやいや、あんなものはもうお祓い箱ですよ、というヤツがもう2、3人出てこなくちゃいかんのじゃないかな(笑)。齋藤さん自身が、そういう姿勢でやってるでしょ。お客として関わろうが、スタッフとして関わろうが、同じなのがシネ・ウインド。関わった以上は出しゃばらなければ、ということは言いたいな。
※1月23日、シネ・ウインドにて
テープ起こし・構成 岸じゅん
聞き手・文・構成 市川明美
■山賀博之…株式会社ガイナックス代表取締役。1962年、新潟市生まれ。新潟県立新潟南高等学校卒業、大阪芸術大学芸術学部映像計画学科(現・映像学科)中退。1984年に株式会社ガイナックスを設立。1987年に映画「王立宇宙軍 オネアミスの翼」で監督デビュー。現在、新作「蒼きウル」製作中。
■「王立宇宙軍 オネアミスの翼」…1987年 / 日本 / 監督・脚本 山賀博之 / 声の出演 森本レオ 他 / 音楽 坂本龍一 / 製作費8億円 シネ・ウインドでは88年7月に、8日間1日4回、全回監督トーク付上映を実施。
■株式会社ガイナックス(GAINAX)…アニメーション等のメディア制作を中心に行う会社。「新世紀エヴァンゲリオン」「ふしぎの海のナディア」「トップをねらえ!」など、ヒット作多数。